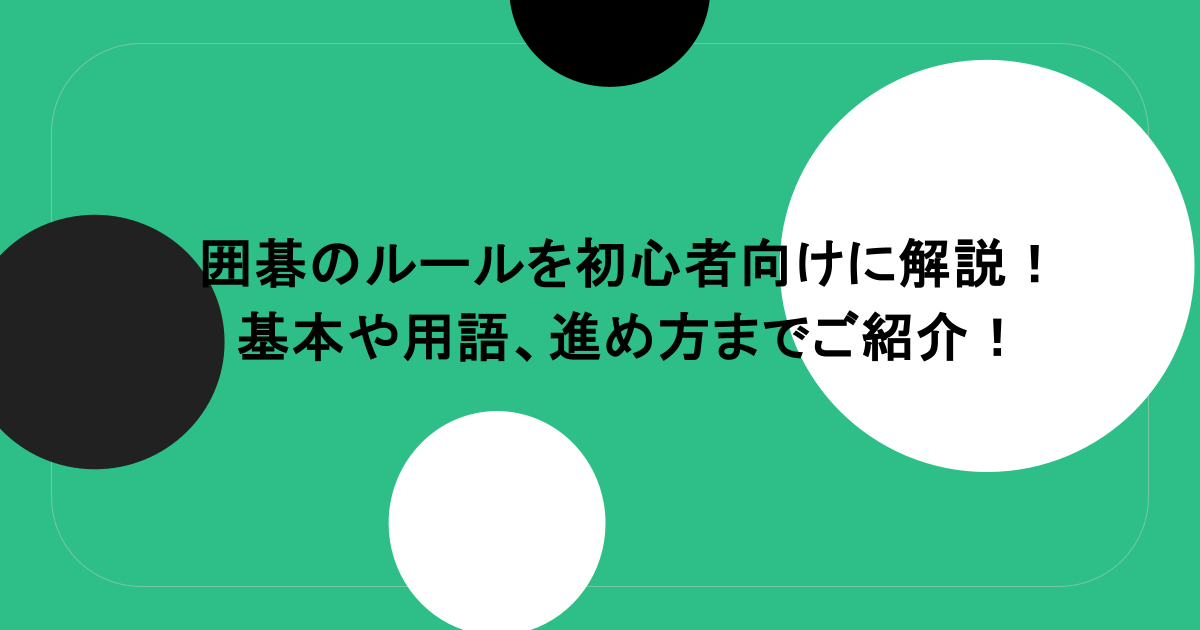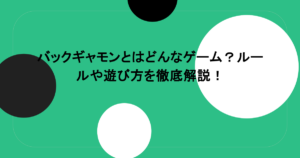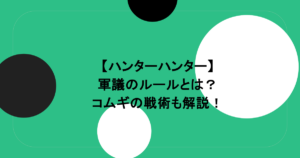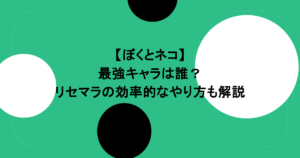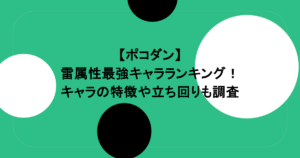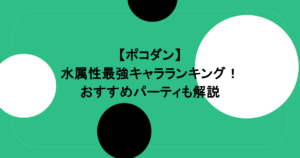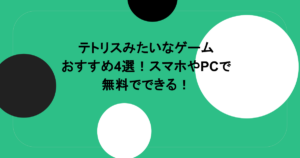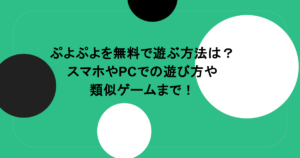囲碁はとても歴史のあるボードゲームで、奥深い戦略が魅力的なボードゲームですが、囲碁のルール自体は意外とシンプルです。
この記事では、囲碁の基本的なルールからゲームの進め方、勝敗の決め方まで、わかりやすく解説していきます。「囲碁のルールって難しそう…」と感じている方は、是非参考にしてみてくださいね!
これだけは押さえたい!囲碁の基本ルール
まずは、基本的な囲碁のルールを見ていきましょう。
ゲームの最終目標:より多くの「地」を囲うこと
囲碁は、自分の色の石で囲んだ空の交点、つまり「地」を相手より多く作ることを目指す陣取りゲームです。囲碁では、相手の石を取ることが重要視されがちですが、それはあくまで「地」を確保するための「手段」であり、目的ではありません。
石の置き方:黒からスタート、交互に一手ずつ
基本的に黒石を持つプレイヤーが最初に打ちます。プレイヤーは、黒、白、黒、白と交互に、空いている好きな交点に石を一つずつ置いていきます。
また、一度置いた石は動かせません。
石の取り方:相手の石の「呼吸点」を塞ぐ
石から直接線で繋がっている隣の空き交点を「呼吸点(こきゅうてん)」と呼び、単体の石や繋がった石のグループの呼吸点が、すべて相手の石で塞がれてしまうと、盤上から取られてしまいます。
取った相手の石は「アゲハマ」と呼ばれ、自分のものとして盤の脇に置いておきます。これは後で点数計算に使います。
打てない場所:着手禁止点とコウのルール
囲碁にも打てない場所が存在します。
一つは、石を置いた瞬間にその石の呼吸点がゼロになってしまう場所には打てません(原則として)。ただし、その手で相手の石を取れる場合は例外的に打つことができます。これを着手禁止点といいます。
次に、特定の状況で、お互いが一つの石を取り合い、同じ盤面が無限に繰り返されるのを防ぐためのルールがあります。これをコウといい、相手は一度別の場所に打つ必要があります。少し複雑ですが、「同じ場所ですぐに取り返せないことがある」と覚えておきましょう。
知っておくと便利!囲碁の基本用語
囲碁には特有の用語があります。いくつか基本的なものを覚えておくと、解説を読んだり対局を振り返ったりするのに役立ちます。
| 用語 | 読み方 | 簡単な意味 |
| アタリ | アタリ | 次の手で石が取られる状態 |
| 地 | ジ | 自分の石で囲んだ空き交点(陣地) |
| ダメ | ダメ | 石の呼吸点。または、どちらの地でもない中立の点 |
| コウ | コウ | 特定の石の取り合いに関する特別ルール |
| アゲハマ | アゲハマ | 自分が相手から取った石 |
| 呼吸点 | コキュウテン | 石から直接線で繋がっている空きマス |
ゲームの流れを解説
囲碁の一局がどのように進んでいくのか、大まかな流れを見てみましょう。
ゲームの始め方
同じくらいの強さなら「ニギリ」という方法で石を握って先番(黒番)を決めます。
実力差がある場合は、弱い方が黒を持ち、先に決められた数の石を盤上の星に置いてから始めます。これを置き碁と言い、置き碁では、置き石を置いた後は必ず白番から打ち始めます。
囲碁の三段階
布石・中盤・ヨセ 一般的に、囲碁の一局は以下の三段階で進みますが、境界はあいまいです。
- 序盤(布石):ゲームの初期段階。主に盤の隅や辺に石を配置し、将来の地の候補地を効率よく確保することを目指します。広い範囲への影響力を考えましょう。
- 中盤:本格的な戦いの始まり。相手の模様に侵入したり(打ち込み)、自分の石を守ったり、相手の石を取ったりします。石同士の接触が増え、攻防が激しくなる段階です。
- 終盤(ヨセ):大きな地の境界線がほぼ決まった後の段階。お互いの地の境界線を確定させ、ダメを埋めていきます。終盤の一手が勝敗を分けることもあります。
勝敗はどう決まる?
熱戦の末、囲碁の勝敗は最終的な地の大きさで決まります。
ゲームの終わり方
お互いに、もう盤上で打つ場所がないと判断したら終了です。一方が「パス」をし、相手も続けて「パス」をすると対局終了となります。
終了後、盤上に残っている「死に石」(取られることが確定している石)を盤上から取り除き、相手のアゲハマに加えます。この判断は少し難しい場合もあります。
点数計算
どちらの地でもないダメをお互いの石で埋め、自分の石だけで完全に囲んでいる空の交点の数を数えます。これが自分の「地」の得点です。
またアゲハマを、相手の地の中に埋めて、相手の地の得点を減らします。
最終的な得点を比較し、点数が多い方が勝ちです。
まとめ
囲碁の目的は「自分の石で相手より多くの地を囲むこと」です。石は「交点」に置き、相手の石は「呼吸点」を全て塞いで取ります。「アタリ」や「コウ」といったルールもポイントです。最初から全てを完璧に理解するのは難しいので、まずは9路盤などから始めてみてくださいね!